改正労働基準法解説レポート
令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。
フレックスタイム制の労使協定で定める事項
始業・終業時刻の自主決定が大原則
フレックスタイム制を導入するためには、以下のことが必要です。
対象となる労働者の範囲
「全労働者」あるいは「特定の職種の労働者」と定めることができます。
個人ごと、課ごと、グループごと等、様々な範囲も考えられます。
ただし、制度の性格上、勤務時間を厳守する必要のある職務の従事者(たとえば、受付窓口や警備など)、精・皆勤手当を支給している業務に従事する労働者は、対象にできません。
清算期間(1ヶ月以内)
(フレックスタイム制を実施したとき、実際に労働した時間とあらかじめ定めた総労働時間との清算をするための期間)
清算期間については、その長さと起算日を定めることが必要です。単に「1ヶ月」とせずに、「毎月1日から月末まで」、などと定めることが必要です。
1週間単位も可能ですが、賃金計算期間に合わせて1ヶ月とする場合が一般的です。
労働時間
清算期間内における総労働時間(平均して週40時間、特例適用事業では週44時間まで)、および標準となる1日の労働時間は、清算期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内となるように定める必要があります。
別の言い方をすると、清算期間における総労働時間は、次の式で計算される清算時間における法定労働時間の総枠の範囲内で定めなければなりません。
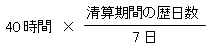
例えば、1ヶ月のフレックスタイム制とすると、以下が清算期間中の法定労働時間となります。
- 1ヶ月が31日の月は 177.1時間
- 1ヶ月が30日の月は 171.4時間
- 1ヶ月が29日の月は 165.7時間
- 1ヶ月が28日の月は 160.0時間
ただし、この場合も曜日の周り方によって、オーバーすることがあります。
時間外労働
フレックスタイムの場合、毎日に始業・終業時刻の決定は労働者に委ねられたという前提が存在します。
このため、使用者は労働者の同意を得ることなく時間外労働を命ずることはできないし、同様に、使用者が拘束時間を決める会議・出張も命じることができないという見解もあります。
しかしながら、労働者が決定できるのは「始業」「終業」の時刻であることから、労働者が決めた終業時間を超えて使用者が時間外労働を命じることができないと言い切ることも不自然です。
実務的には、フレックスタイム制を採用した場合の時間外労働は1日単位では判断せず、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間で計算されます。
したがって、時間外労働に関する協定についても、1日の延長時間について協定する必要はなく、清算期間を通算して延長時間及び1年間の延長時間の協定をすることになります。(昭和63.1.1 基発1号)
標準となる1日の労働時間
労使協定では、清算期間における法定労働時間の総枠の範囲内で、例えば1ヶ月160時間というように各清算期間を通じて一律の時間を定める方法のほか、清算期間における所定労働日を定め、所定労働日1日あたり7時間というような定めをすることもできます。
フレックスタイム制を採用している労働者がその清算期間内において有給休暇を取得したときには、その取得した日については、標準となる労働時間を労働したものとして取り扱います。
このため、標準となる労働時間を定めておかなければ不都合が生じます。
標準労働時間として「8時間」という定めをしておけば、労働者が年次有給休暇を取得したときに支払われる賃金は8時間相当と見なされ、また、フレックスタイムが適用される労働者が事業場外労働をし、その労働時間が算定しがたいときは8時間労働したものとして計算することができるようになります。
なお、この制度導入の場合でも1週1日または4週4休の休日を取らせる必要があります。
コアタイム
コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)を定める場合は、その時間帯の開始・終了時刻を定めなければなりません。
コアタイムとは、労働者が必ず労働しなければならない時間帯のことをいいます。
コアタイムは必ず設けなければならないものでは、ありません。
この場合(オールフレックス)は、従業員はいつでも自由に出社・退社できることになります。
コアタイムを定める場合は、この開始・終了の時刻を明確にしておかなければなりません。
コアタイムは必ず勤務すべき時間帯ですから、コアタイムに「遅刻・早退・欠勤」の制度を設けることはできます。
「コアタイムの遅刻、早退が2回に及んだ場合は1回の欠勤として1日分の減給制裁扱いとしてカットする」という就業規則の定めも可能です。
また、コアタイムの遅刻等を、昇給・賞与・昇格の査定に反映させることも問題なくできます。
関連事項:降格・減給→
フレキシブルタイム
フレキシブルタイムに制限を設ける場合にはその時間帯の始・終了の時刻を定めなければなりません。
フレキシブルタイムとは、労働者がその選択により労働することができる時間帯のことをいいます。
フレキシブルタイムは必ず設けなければならないものでは、ありません。
ただし、コアタイム、フレキシブルタイムの両方を設ける場合は、フレキシブルタイムは極端に短いものであってはなりません。(昭和61.1.1 基発1号)
というのも、極めて短時間では、「始業・終業を労働者の決定に委ねる」というフレックスタイムの主旨に反するからです。
フレックスタイム制の場合にも、使用者には労働時間の把握義務があります。
したがって、フレックスタイム制を採用する事業場においても、労働者の各日の労働時間をきちんと行わなくてはなりません。(昭和63.3.14 基発第150号)
その他
起算日を定める必要があります。
就業規則その他これに準ずるもの又は労使協定において、清算期間の起算日を明確に定めておく必要があります。
フレックスであっても、使用者は労働時間管理が免れない
フレックスタイムは、始業・終業時刻が労働者に任せられている制度です。
しかしながら、だからといって、使用者は労働者が何時間働いたかわからないというのでは、労働時間の算定ができず、したがって、時間外労働の計算もできないことになります。
使用者に労働時間の把握義務がある。
フレックスタイム制を採用する事業場においても、各労働者の各日に労働時間の把握をきちんと行うべき。
(昭和63.3.14 基発150号)
このため、管理者には、従業員各自の就業時間の把握と、適正な運用がされるための指導が求められます。
労働時間の管理は、タイムレコーダーや勤務表を利用するほか、労働者の自主記録により把握査定することもできます。
また、フレックスタイム制は、従業員がバラバラに出退勤する労働時間制であるため、部下の業務管理において中間管理職の負担が重くなる可能性があります(良心的な管理職の中には、一番早く出社する部下に合わせて出社し、一番遅く帰る部下が退社するまでつき合う者がいます)。
