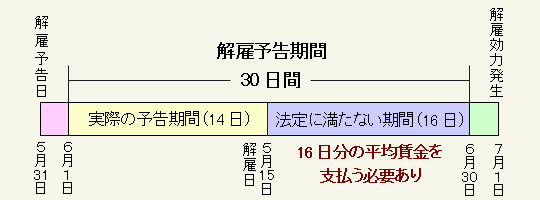解雇予告を行なう場合の原則
30日前の予告が原則
使用者が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければなりません。(労働基準法第20条)
また、解雇予告は解雇の日を特定しなければなりません。
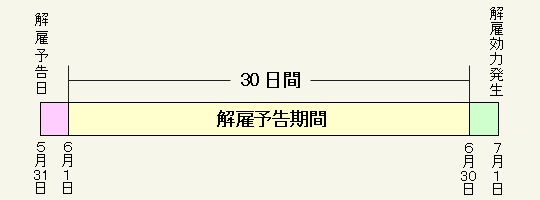
郵送による場合は、投函した日ではなく、相手方に郵便が到着した日が予告日となります(民法第97条)、その翌日から30日後が解雇日となるように、解雇日を設定しなければなりません。
また、解雇予告期間の日数計算は、解雇通告の翌日から起算します。
消滅時効は権利を行使することができる時から進行する。
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
例えば、6月30日に解雇するのであれば、遅くとも5月31日に解雇の予告をしておかなければなりませんが、郵送によって解雇を通知しようとして5月31日に発送しても、労働者に届くのが6月1日だったとすると、6月2日から起算されるので、予告日数が1日不足することになります。
「解雇予告手当を支払えば民事上解雇が有効になる」と考えている人がいますが、これは誤解です。
「予告手当を支払えば労基法20条違反にならない」、つまり刑事罰(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金、法第119条)は受けないということであって、民事上解雇が有効か無効かということは、別に判断されます。
即日解雇の場合は30日分の手当を
30日前に解雇の予告をしない使用者は、予告に代えて30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。
予告期間が30日に満たない場合は、その日数分の予告手当を日割りで支払うことになります。
計算方法について詳しくは:平均賃金→
なお、行政解釈では、即時解雇であれば、少なくともその申し渡しと同時に予告手当を支払わなければならないとされています。(昭和23.3.17 基発第464号)
解雇予告日数が不足する場合
30日の解雇予告手当の数え方については、特に労働基準法に定めがないため、民法の一般原則に従って計算することになります。
すなわち、解雇予告した当日は解雇予告期間に含まれず、予告した日の翌日を解雇予告期間の初日として計算することになります。(民法140条)
解雇予告期間と解雇予告手当の計算例
例えば、前出の例で5月31日に解雇予告を行う場合を見てみましょう。
この場合は6月1日が解雇予告期間の初日となりますから、そこから30日経過後の6月30日が予告期間の最終日(=解雇日)となり、契約期間はこの日いっぱいで終了することになります。
したがって、30日分の解雇予告手当を支払うことになります。
しかし、下図のように、6月15日付けで解雇する旨の予告を5月31日に行った場合は、6月1日から起算して6月15日までは14日しかありませんから、30日に足りない16日分の平均賃金を支払う必要があるわけです。