給付の種類・内容
給付の内容
給付額は、物価等によって変化します。
※以下の金額は2024年7月現在のものです。正確な金額が知りたい方は、日本年金機構へお問い合わせください。
老齢基礎年金
年金額
816,000円(年額 2024年7月現在)
※保険料納付月数が40年に満たない場合には、次の計算式によります。
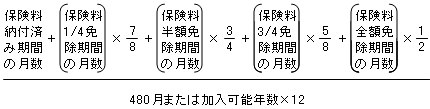
付加年金
200円×付加保険料納付月数
支給要件
保険料納付・免除期間等が10年以上。
65歳からの支給が原則ですが、60歳から65歳未満の繰り上げ減額制度、66歳以降の繰り下げ増額制度があります。
障害基礎年金
年金額(年額、2018年3月現在)
1級 1,020,000円
2級 816,000円
ただし、18歳以下(年度末まで)の子ども、または20歳未満の障害者がいる場合には、2人目は224,300円、3人目以降は74,800円加算されます (年額、2024年7月現在)。
支給要件
初めて医師や歯科医師の診療を受けた初診日に、被保険者であるか、あるいは被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること。
初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、あるいはこの期間内に傷病が治った場合にはその治った日に、障害等級1級または2級程度の状態にあること。
保険料滞納期間が、強制被保険者期間の1/3未満であること。
20歳前に障害者となった人には、20歳になったときから支給される。
遺族基礎年金
年金額(年額、2024年7月現在)
妻が受けるとき・・・1,050,800円(子が1人の場合)
子が受けるとき・・・816,000円
ただし、受給権者によって生計を維持しているその者の子がある場合は、障害基礎年金と同様の加算があります。
支給要件
死亡した人が、以下のいずれかであること。
- 被保険者
- 被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満のもの
- 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付・免除期間等が25年以上である者に限る)
- 保険料納付・免除期間等が25年以上である者
保険料滞納期間が、強制被保険者期間の1/3未満であること。
死亡者によって生計を維持されていた子(18歳到達年度の末日まで、あるいは一定の障害状態にある20歳未満であって現に婚姻していない子)のある妻または子に対して支給される。
付加年金
支給額
200円×付加保険料納付済期間の月数(2024年7月現在)
支給要件
付加保険料(月額400円、2024年7月現在)を納めた人で、老齢基礎年金の受給権を取得した者
寡婦年金
年金額
夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の3/4
支給要件
第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上の夫が、老齢基礎年金を受給しない、あるいは障害基礎年金の受給権者となったことがないまま死亡した場合、婚姻関係が10年以上の妻に60歳から65歳に達するまでの間支給される。
死亡一時金
支給額
保険料納付月数によって、120,000円~320,000円が支給されます。
また、付加保険料を3年以上納めている場合には、8,500円加算されます。
支給要件
第1号被保険者としての保険料納付済期間等が3年以上の人が、老齢・障害基礎年金を受給しないまま死亡した場合に、死亡者と生計を同じくしていた遺族が、遺族基礎年金を受けられないときに支給される。
脱退一時金
支給額(最後に保険料を納付した月が2024年(令和6年)4月から2025年(令和7年)3月の場合)
保険料納付期間によって、50,940円~509,400円の一時金を支給する(2024年7月現在)
支給要件
6ヶ月以上保険料を納付した外国人が年金を受給しないまま帰国し、2年以内に請求したときに支給する。
保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数の合計が6ヶ月以上必要。
保険料納付期間などが10年に満たない場合
次に挙げる期間等と、保険料納付期間や免除された期間などを合わせて10年以上あれば、老齢基礎年金が支給されます。
ただし、これらの期間は受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には反映されません。
- 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間で、厚生年金(旧法を含む)の被保険者であった期間のうち、20歳前および60歳以後の期間
- 昭和36年4月1日以後、厚生年金保険や共済組合等に加入していた人の配偶者または学生であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの期間のうち、任意加入したにもかかわらず、保険料を納付しなかった期間
- 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間のうち、国民年金の任意脱退の承認を受けて被保険者とされなかった期間
- 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間のうち、日本国内に住所を有さず、日本国籍を有していた者で任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間のうち、国会議員であったため国民年金に任意加入できなかった期間
厚生労働省による国税庁への強制徴収委任
年金保険料の悪質な滞納者について、厚生労働省は国税庁に強制徴収を委任することができます。
対象は、滞納期間が13ヶ月以上、財産を隠ぺいしているおそれがある、前年の所得が1,000万円以上、かつ、徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められない者です。
