給付の額(老齢厚生年金)
60歳~64歳の年金受給額は以下の部分の合算額となります。
定額部分+報酬比例部分+加給年金額
ただし、生年月日によって支給開始が移行しますので、注意が必要です。
定額部分
定額部分は、国民年金に相当する一律分だと考えれば、理解しやすくなります。
定額部分は次の(1)と(2)を比較して、どちらか高い額で決められます。
(1) 平成16年法改正による計算式(原則)
1,696円(令和6年度単価)×1.0~1.875(政令で定める率)×被保険者期間(※)
※被保険者期間の月数には生年月日に応じて下記の上限が定められています。
| 生年月日 | 上限 |
|---|---|
| 昭和4年4月1日以前 | 420月(35年) |
| 昭和4年4月2日~昭和9年4月1日 | 432月(36年) |
| 昭和9年4月2日~昭和19年4月1日 | 444月(37年) |
| 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 456月(38年) |
| 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 468月(39年) |
| 昭和21年4月2日以後 | 480月(40年) |
報酬比例部分
報酬比例部分は、過去に納めた保険料応じて加算される部分です(最低保障あり)。
この額は、以下の(1)、(2)を比較して、いずれか高い額で決められます。
(1) 平成16年改正水準による計算式(原則)
年金額=①+②の合計
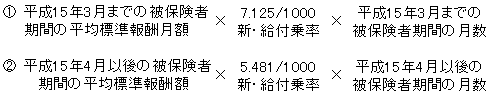
※平均標準報酬額および平均標準報酬月額は、平成16年改正の再評価率24年度分に基づいて算出します。
(2) 平成12年改正水準による計算式(平成6年改正水準の保障)
年金額=(①+②)×1(昭和13年4月以降に生まれた方は0.998)
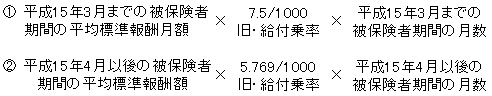
※平均標準報酬額および平均標準報酬月額は、平成6年改正の再評価率に基づいて算出します。
加給年金額(定額部分が加算される場合に限る)
- 配偶者(65歳未満)・・・234,800円
- 第1子および第2子・・・234,800円
- 第3子以降・・・各 78,300円
※年額です。「子」とは、18歳年度末(障害のある子は20歳未満)までです。
(令和6年4月)
このように、複雑な要素で成り立っている老齢厚生年金の額を導き出すのは容易ではありません。
しかし、荒っぽい説明ですが、「全期間加入していた人が満額受け取るとなると、月10万円弱くらい。途中で抜けていれば、それに応じて減額される。年齢が若ければさらに減る」と値踏みしておけば、大きく外れることはないといえるでしょう。
つまり、毎月徴収される保険料から予想される額より、かなり少ないのが実感ということです)。
65歳以上の年金
報酬比例年金額+加給年金額
報酬比例年金額は、60歳~64歳の報酬比例部分と同じで、加給年金額は、60歳~64歳の加給年金額と同じです。
このほか、老齢基礎年金(=定額部分の代わりとなる)が支給されます。
