夫と連動した妻の年金加入
夫の年金種別の変化と連動した妻の年金加入パターン
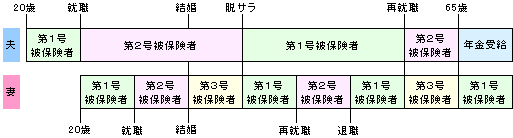
国民年金の被保険者種別が変更された場合の対応
| (1) | 第1号被保険者になったら | 自分で住所地の区・市役所で手続き |
| (2) | 第2号被保険者になったら | 勤務先に手続きをしてもらう |
| (3) | 第3号被保険者になったら | 配偶者の勤務先に加入手続きしてもらう |
専業主婦の場合でも、配偶者の年金加入によって自分の加入する年金の種類が異なってきます。
特に、配偶者が第2号(サラリーマン)から第1号(自営)に変更した場合は、自分で手続きしなくてはならないので要注意です。
また、パートタイム労働者が退職して、配偶者の被扶養者になった場合などに、第2号から第3号被保険者への変更手続きをしないでいると、将来、無年金になってしまうことがあります。
国民年金加入が義務付けられているにもかかわらず、そのまま放置しておくと、年金受給に必要な期間が足りなくなったり、年金額が減ったり、障害時の保障が受けられなくなったりします。
第3号から1号への変更手続きは「被保険者種別変更届」によって行います。
失業給付受給時の注意
配偶者の年収が130万円を超える見込みの場合は被扶養者になれないため、第3号被保険者として認められません。したがって、第1号被保険者になります。
失業給付の受給中も第3号被保険者になれるのは、失業給付に基本手当の日額が約3,611円以下であることが目安です。
ほとんどの場合、基本手当の額はそれを上回るので、失業給付の受給期間中は大半の人が第1号被保険者になります。
関連事項:遺族になったとき→
離婚したとき
3号分割制度
平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。(請求にあたっては、当事者双方の合意は必要ありません)
- 婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
- 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
合意分割制度
平成19年4月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当すると、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することができる制度です。
- 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
- 当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。)
- 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
