改正労働基準法解説レポート
令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。
変形労働時間制とは
1週間あたり40時間のバリエーション
変形労働時間制度は上記のように多種多様ですから、一つ一つ個別に理解しようとすれば頭が混乱してしまいます。
労働時間は「原則として週40時間(特例事業の場合は44時間)」ということを、まず、押さえておきましょう。
これまでの労働法では、労働時間=1日8時間が原則でした。
しかし、改正により、1週間=40時間が基本となっています。
これは、一見小さな違いに見えますが、実は考え方の面では大きな変更だといえます。
すなわち、労働時間の量を"点"でとらえるか、"総量"としてとらえるか、という違いです。
わかりやすく言うと、「平均して週40時間以内に収まれば、いろんなバリエーションがあってもいいじゃないか」ということです。
ただし、あらかじめ就業規則による定めが必要で、使用者の都合で勝手に変えられる制度ではありません。
変形期間を平均し週40時間の範囲内であっても使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しないものであること。
(昭和63.1.1 基発1号、平成3.1.1 基発1号)
労働の波をどう押さえるか
会社の中での仕事量には、「波」があります。
労働時間が一定だと、労働者は仕事量が増大したときは残業しなければならず、使用者はこれに時間外手当という出費を余儀なくされます。
逆に仕事量が少ないときには、労働者は、怠けているように思われたら嫌なので、本当なら6時間ですむ仕事を8時間かけてやることもあるでしょう。
こうした波に合わせて、あらかじめ労働時間そのものを設定しようとするのが、変形労働時間の考え方です。
その波の周期は仕事の内容によって様々でしょうが、大きくいって1年を単位とした波と、1ヶ月を単位とした波があります。
1ヶ月周期、たとえば月末と月初めが多忙で、月半ばは暇ということならば、「1ヶ月単位の変形労働時間」の採用を検討することになるでしょう。
あるいは、1年周期、たとえば年度末は多忙で、2月8月は閑散期ということがあらかじめわかっているならば、「1年単位の変形労働時間」の採用を検討することになります。
いつ仕事が終了したか把握が難しい業務形態なら、「みなし労働」が適していますし、出社・退社時間を労働者に委ねられるならフレックスタイム制、クリエイティブな仕事なら裁量労働制が検討対象となります。
1ヶ月単位の変形労働時間制
会社が労使協定または就業規則で、各日、各週の労働時間をあらかじめ具体的に定め、1ヶ月以内の一定の期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を超えないように決めたときは、ある日の労働時間が8時間を上回ってもかまわないし、ある週の労働時間が法定時間を超えてもよいことになっています。
これによって、ある日の労働時間を8時間を超えて長くしたときは、他の日にその分だけ短くし、週平均が法定労働時間を超えないようにしなければなりません。
1ヶ月単位の変形労働時間制とは、以下の要件を備えることにより採用できる制度です。
- 各事業所に定められている就業規則その他これに準ずるもの、または労使協定により
- 変形労働期間を1ヶ月以内とし
- 期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間(週40時間、特例適用事業の場合は44時間)を超えない範囲で
- 休日を1週1日もしくは4週4休確保し
- 期間中の各日、各週の所定内労働時間を予め特定すること
なお、就業規則等または労使協定に規定する事項は、以下の通りです。
就業規則等・労使協定共通
| (1) | 1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間(特例適用事業の場合は44時間)を超えない旨の定め |
| (2) | 労働日、労働時間の特定 |
| (3) | 変形期間の所定労働時間 |
| (4) | 変形期間の起算日 |
労使協定の場合(上記にプラスして)
| (5) | 変形期間 |
| (6) | 対象となる労働者の範囲 |
| (7) | 変形期間中の各日及び各週の労働時間 |
| (8) | 協定の有効期間 |
また、就業規則による場合は就業規則の変更ですので当然(労働基準法89条)、労使協定による場合も協定の有効期間を定め、労働基準監督署に届ける必要があります。
この制度が適しているのは、以下のような場合です。
- 交替勤務制による職場
- 連続して業務に従事する方が効率がいい業務(たとえばタクシー運転手の業務)
- 1ヶ月単位でみた場合に繁閑がある業務
1ヶ月単位の変形労働時間制の導入例
月末の労働時間を増やす
1日~24日が1日6時間30分労働(土・日休日)、25日以降が1日9時間労働(日休日)
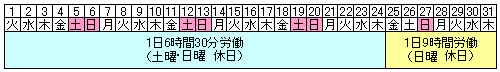
2週間を単位とする変形制
1日7時間15分労働で隔週土日が休日
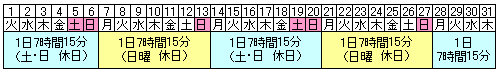
1日10時間労働、週休3日制
1日10時間労働で金土日が休日
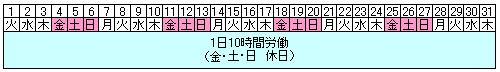
1年単位の変形労働時間制
平成5年の労働基準法改正で、労使協定を締結することを条件に、1年単位の変形労働時間制を採用することができるようになりました。
この制度は、それまでの3ヶ月単位の変形労働時間制の変形期間を1年に延長したものです。
季節などによって業務の繁閉にあわせて労働時間を少なくし、全体として労働時間を短縮することを目的にした制度です。
その導入要件は下記のようになります。
- 労使協定(書面)において
- 期間1年以内(3ヶ月、6ヶ月でもいい)を変形期間とし
- 変形期間平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例適用事業も40時間)を超えない範囲で
- 1日10時間、1週52時間を限度として、かつ、対象期間に連続して労働させることができる日数の限度は6日とされ、特定期間(業務が繁忙であるとして労使協定中で定められた「特定期間」)における連続して労働させることができる日数の限度は、1週間に1日の休日が確保できる日数(連続12日が限度になる)とされ
- 対象期間が3ヶ月を超える場合は、対象期間における1年当たりの労働日数の限度が280日とされ
- 1週48時間を超える週は連続3以下であること
- 3ヶ月ごとに区分した各期間において、48時間を超える週は3以下であること
- 変形期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を特定するとともに
- 当該労使協定を所轄労働基準監督所長に届出ること
なお、労使協定において取り決める必要がある協定事項は次の通りです。
| (1) | 対象となる労働者の範囲 |
| (2) | 対象期間、起算日 |
| (3) | 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間) |
| (4) | 対象期間における労働日とその労働日ごとの労働時間(ただし、対象期間を1ヶ月以上の期間ごとに区切ることとしたときには、最初の区分期間の労働日とその日の労働時間を特定して、残りの区分期間については各々の労働日数と総労働時間数) |
| (5) | (4)の対象期間を1ヶ月以上の期間ごとに区切ることとしたときの次回以降の各期間の労働日やその日の労働時間の特定に関する定め(次回以降の各期間の労働日やその日の労働時間は、各期間初日の30日前に労働者(従業員)の過半数代表の同意をえて決めておかなければなりません) |
| (6) | 当該労使協定の有効期間 |
詳しくは: 1年単位の変形労働時間制とは→
年間休日カレンダーの作成
導入にあたっては、年間の休日カレンダーを作って対処されています。
1ヶ月変形労働時間と1年変形労働時間の比較
| 項目 | 1ヶ月変形労働時間制 | 1年変形労働時間制 |
|---|---|---|
| 1日の所定労働時間 | 制限なし | 10時間以内 |
| 休憩時間 | 労働時間が6時間を超えるときは45分、8時間を超えるときは60分 | 同左 |
| 1週の所定労働時間 | 制限なし | 52時間以内 |
| 週休日 | 週に1日 | 同左 |
| 変形期間中の週平均労働時間 | 40時間以内 | 同左 |
| 各日の始業及び終業時刻 | 就業規則 において記載する | 同左 |
| 労使協定の締結 | 必要なし | 必要あり |
| 労使協定の労基署への届出 | 必要なし | 必要あり |
1週間単位の非定型的変形労働時間制
日ごとの業務に著しい繁閉が生じることが多く、かつその繁閉が定型的に定まっていない場合に、労働時間のより効果的な配分を可能とし、全体としての労働時間を短縮しようとするものです。
この制度は、規模30人未満の小売業、旅館、料理および飲食店の事業に限られます。
その業務の繁閑が定型的に定まらず、就業規則や労使協定等で労働時間の始業・終業時刻をあらかじめ定めることが困難な業務において、忙しい日には長く働く代わりに、暇な日には労働時間を短縮して総体的には労働時間の短縮が図れるための制度で、その導入要件は、労使協定により以下の通りとなります。
| (1) | 1週間単位の非定型変形労働時間制をとること |
| (2) | 1週間の所定労働時間を40時間以内(特例適用事業も週40時間以内)、1日について10時間を上限として、使用者がこの1週間の開始日までにその週の各日の労働時間を書面で通知することと定め |
| (3) | 変形労働時間制を採る一週間の起算日とその期間を定め |
| (4) | 通知の時期、特別な事由があるときの変更手続を定め |
| (5) | さらにその労使協定を所轄労働基準監督所長に届出ること |
この制度の場合も、1週1日もしくは4週4休の休日を確保する必要があります。
この制度は、各日の労働時間が相当前に定まっていないために、使用者が1週間の開始前に各日の労働時間の通知をするという制度です。
1週間の開始前に通知されるといっても週ごとに各日の労働時間が変わる(毎日変わる)わけですし、緊急でやむをえない事由のあるときは通知した労働時間を前日に変更することもできます。
労働者にとっては自由な時間が確保しづらくなります。
労働基準法施行規則12条の5第5項にあるように、使用者は、この制度で労働させる場合には、1週間の各日の労働時間を決める際に労働者の意思を充分に尊重し配慮することが重要です。
詳しくは:1週間単位の変形労働時間制とは→
