改正労働基準法解説レポート
令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。
時間外手当
割増賃金
労働基準法では、1日8時間、1週間で40時間(休憩時間を除く)を超え、または週1日の法定休日に働かせる場合は、36協定(時間外・休日労働協定)を労働者の代表者と使用者で締結し、労働基準監督署へ届け出ること、そして割増賃金を支払うことが定められています。
法定労働時間を超えた労働には2割5分以上の割増賃金、法定休日の労働には3割5分以上の割増賃金が必要です。
さらに、午後10時から午前5時までの労働(深夜労働)には2割5分以上の割増賃金が必要です(時間外労働又は休日労働に深夜労働が重なった場合の割増賃金は、それぞれ5割以上、6割以上の割増になります)。
前日の労働が継続して翌日まで及んだ場合には、翌日の所定労働時間の始業時刻までの分は前日の超過勤務時間として取り扱われます。(昭和28.3.20 基発第136号)
また、時間外労働と休日労働が重なっても3割5分以上とされています。
「労使の合意があるので支払わない」という理由は、成り立ちません。
労働基準法第37条は強行規定であり、たとえ労使合意の上で割増賃金を支払わない申し合わせをしても、法第37条に抵触するから無効である。
(昭和24.1.10 基収第68号)
割増は、36協定に反した時間外労働でももちろん必要です。
北錦会事件 大阪地裁 平成13.9.25
病院のヘルパー・炊事婦ら26名が時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当等の請求を行った。
裁判所は総額4,057万円の支払いを命じた。
労働時間制度の変更によって、割増賃金が減る場合もありますが、これを既得権とした請求を認めさせることは困難です。
函館信金事件 函館地裁 平成6.12.22
労働者には時間外労働を求める権利はなく、その意味で、時間外労働に支払われる時間外手当は、従来支払われていたものであっても、既得権としての権利制が弱いものであることは否定できない。
したがって、基本給の低い分を時間外手当によって補っているという現実の状況があるとしても、なお、右時間外手当の減少をもって、不利益制の内容として重視することはできないというべきである。
割増賃金計算の原則
当該時間外・法定休日労働について就業規則、労基法により、通常の労働時間または労働日の賃金の2割5分以上、法定休日の労働には3割5分以上の割増し率で計算して支払わなければなりません。
また、深夜(原則午後10時から午前5時まで)に労働させた場合も2割5分以上の割増賃金を払わなくてはなりません。
残業が深夜に及ぶときはあわせて5割増し以上となります。シフト勤務などにより法定時間の範囲内で行われる深夜業の場合は2割5分増しです。
| 所定外労働の種類 | 割増率 | 備考 |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 0.25 | 原則8時間の超過 |
| 法定休日労働 | 0.35 | 法定休日労働の場合 |
| 深夜労働 | 0.25 | 午後10時~午前5時 |
| 時間外+深夜労働 | 0.50 | 0.25+0.25 |
| 法定休日労働+深夜労働 | 0.60 | 0.35+0.25 |
| 法定休日労働+時間外労働 | 0.35 | 0.60ではない |
通常の賃金を計算するときは、定期的に決まって支払われるすべての賃金のうちから、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金を除くことが可能です。
これを、日給制の場合は1日の所定労働時間数で割り、月給制の場合は月の所定労働時間の合計(月のよって合計時間数が異なる場合は、1年間における1ヶ月当たりの平均時間数)で割って算出します。
所定労働時間とは、各事業所の労働契約や就業規則などで定められた実労働時間です。
所定労働時間 1日7時間の場合(例1)
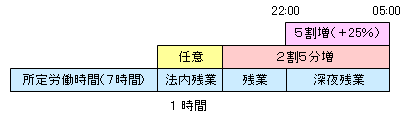
休日労働の場合(例2)
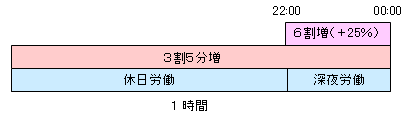
※法定外休日労働には、法律上割増賃金を支払う義務はありません。しかし、実態としては法定休日と同様の3割5分増し、または時間外労働と同じ2割5分増とする企業が多いです。そうしないと、実務上の取扱いがかなり煩雑となるからです。
※法定内残業
残業のうち、法定労働時間内の部分は法内残業と呼ばれます。
なお、平日から勤務が法定休日に繰り越した場合、法定休日出勤が平日にずれこんだ場合については、休日の暦日原則(昭和23.4.5 基発第535号=休日は午前0時から翌午前0時までとされる)により、次のようになります。
通常勤務日の深夜残業が翌日の法定休日に食い込んだ場合(例3)
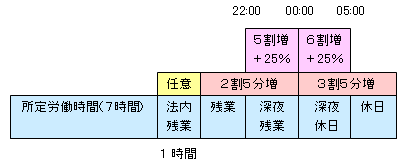
※休日が法定休日なのか、単なる会社の定める休日なのかによって違います(法定の休日は1週に1回または4週に4回)。
休日労働の深夜残業が翌日の通常勤務日に食い込んだ場合(例4)
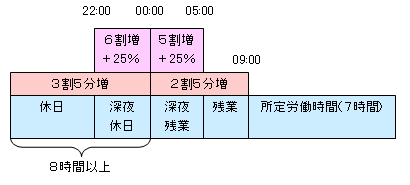
※この例は、正規の勤務時間開始を午前9時、休日労働時間は8時間超を想定したものです。翌日の勤務開始時間までが、前日の超過勤務と見なされます。
※なお、上記2例は連続勤務時間が相当長時間に及びます。割増賃金を払えば時間外手当についてはクリアしますが、健康管理等、別の意味でいささか問題あり、と言わざるを得ません。
※法定休日
法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が休日労働となる。
したがって、法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合及び法定休日の勤務が延長されて翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が3割5分以上の割増賃金の支払いを要する休日労働時間となる。
※時間外労働
休日労働と判断された時間を除いて、それ以外の時間について法定労働時間を超える部分が時間外労働となる。この場合、1日及び1週間の労働時間の算定に当たっては、労働時間が2暦日にわたる勤務については勤務の開始時間が属する日の勤務として取り扱う。
(平成6.5.31 基発第331号)
平成22年4月1日より下記2件の法律が施行されました!
限度時間を超える時間外労働の労使協定を締結する場合、2割5分を上回る割増賃金率を設定するよう努力義務
1日8時間、1週40時間といった法定労働時間を超えて労働する場合、労使協定を締結する必要がありますが、時間外労働には限度時間(1ヶ月45時間や1年360時間以内など)が決められています。
臨時的に限度時間を超えて労働する場合、特別条項付きの労使協定を締結する必要があります。
改正により、この特別条項付き労使協定に定める事項として以下の点が加えられました。
- 限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を定めること。
(延長することができる期間を「1日を超え3ヶ月以内の期間」と「1年間」の両方締結する場合は、それぞれについて割増賃金率を定める必要があります。) - 限度時間を超える時間外労働はできる限り短く設定するよう努めること。
- 限度時間を超える割増賃金率には2割5分を超えるよう努めること。
今回の改正内容は、施行日以降に特別条項付き労使協定を締結、または更新する場合に適用され、1年単位変形労働制に関しても準用されます。
例えば、平成22年1月1日に有効期限を1年として労使協定を締結した場合、平成23年1月1日の更新の際、適用されることになります。
また、労使協定の締結だけでなく、割増賃金率は「賃金の計算方法」に該当する為、就業規則にも定めておく必要があります。
1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は5割増に引上げ
平成22年4月1日より、時間外労働が1ヶ月60時間を超えた場合、超えた部分に対する割増賃金率が2割5分増から5割増へと引上げられる事となりました。また、2割5分引上げられた部分に関しては、労使協定を締結した場合、休暇の付与に代えることができます。
時間外労働の延長限度時間は、1ヶ月45時間(1年単位の変形労働制では1ヶ月42時間)である為、60時間超の時間外労働については特別条項付き労使協定の締結が必要となります。
1ヶ月は暦上での1ヶ月でも、賃金計算期間でも構いません。
※施行日を含む1ヶ月については、施行日から時間外労働を累計して60時間に達した時点より後の時間外労働について、5割以上の割増賃金率で計算します。
例えば、毎月21日~翌月20日までを賃金計算期間とする場合
1)平成22年3月21日~平成22年3月31日…時間外労働10時間
2)平成22年4月1日~平成22年4月20日…時間外労働65時間
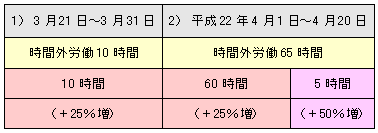
1)10時間と、2)65時間のうち60時間については2割5分増で計算
2)の60時間超え(65時間-60時間)=5時間については5割増で計算
となります。
また、割増賃金率の改正は時間外労働のみで60時間を超えた場合に適用される為、法定休日における労働時間は含まれません。
例えば、週休2日制(所定休日が土日)で日曜日を法定休日(週1日または4週4日の休日)としている会社の場合。
日曜日に労働→休日労働の為、3割5分増で計算(60時間に含まない)
土曜日に労働→時間外労働の為、2割5分増で計算(所定労働日の時間外労働含め60時間を超えた部分は5割増で計算)となります。
時間外労働が1ヶ月60時間を超え、時間外労働が深夜に及ぶ場合、その割増賃金率は5割増に深夜の2割5分増が加わる為、7割5分増となります。
臨時的な事情においてどうしても60時間を超える時間外労働を行わなければならない場合があります。そこで、引上げ分の割増賃金(2割5分増)を支払う代わりに、労使協定を締結することによって、年次有給休暇とは別の有給の休暇を付与する代替休暇を与えることができることになりました。
休暇を付与できるのは今回引上げられた2割5分増分のみであり、時間外労働に対しては今まで通り2割5分増の割増賃金を支払わなければなりません。
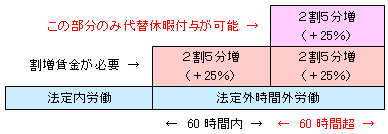
時間外労働が60時間を4時間超えると1時間分の割増賃金となり、
0.25(割増賃金率)×4時間=1時間分
所定労働時間が8時間の会社であれば、時間外労働が60時間を
16時間超えると4時間=半日分 0.25(割増賃金率)×16時間=4時間
32時間超えると8時間=1日分 0.25(割増賃金率)×32時間=8時間
の休暇がとれることになります。
代替休暇付与の労使協定に定める事項
1)代替休暇として与えることができる時間数の算定方法
代替休暇として与えることができる時間の時間数=(1ヶ月の時間外労働時間数-60)×換算率(0.25)
2)代替休暇の単位
「1日または半日」のどちらか
「代替休暇以外の通常の労働時間が支払われる」旨を定めた場合、1時間単位の有給休暇や会社が与えた特別給与などと併用する事も可能
例:代替休暇2時間+有給休暇2時間=4時間→半日休暇
3)代替休暇を与えることができる期間
「時間外労働が60時間を超えた月から2ヶ月以内」
例:6月の時間外労働が76時間となった場合
76時間×1.25は本来支払うべき賃金支払日に支払い、8月末までに代替休暇を取得することになります。
ただし、本人の取得意思があるにもかかわらず、取得できなかった場合は、そのことが判明した賃金計算期間にかかわる賃金支払日に0.25分の割増賃金を支払わなければなりません。
4)代替休暇の取得日および割増賃金の支払日
労使協定の締結はもちろんのこと、代替休暇は「休暇」に該当する為、就業規則の休暇に関する事項にも定めておく必要があります。
※中小企業主には施行後3年間、割増賃金の引上げ、および引上げ部分の代替休暇の規定は猶予されます(当分2割5分増のまま)。
中小企業主とは[資本金の額]または[常時使用する労働者]のどちらかが次に該当するものをいいます。
≪中小企業主の基準≫
| 業務の種類 | 資本金または出資の総額 | または | 常時使用する労働者数 |
|---|---|---|---|
| 小売業 | 5千万円以下 | または | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | または | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | または | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | または | 300人以下 |
所定時間内労働と時間外労働の内容が違った場合
所定時間内は事務で時給1,000円の者が、時給1,500円に定められている業務を、時間外に行うことなどがあり得ますが、この場合、割増賃金の計算基礎となるのは、後者の時間単価です。
休憩時間中に窓口事務や来客当番をさせると、時間外労働となる
休憩時間中に窓口事務、来客当番等に従事させた場合には、その時間は労働時間となるから、その時間と他の労働時間を通算し、1日8時間又は週の法定労働時間を超える場合には、割増賃金の支払義務が生ずる。
(昭和23.4.7 基収第1196号)
なお、このケースでは、休憩時間を別途与えなければ労働基準法34条にも違反します。
行政官庁の許可を得て行う監視断続勤務でも、深夜の割増賃金は必要
監視断続労働の許可を得ている場合においても、深夜業の規定の適用除外はされないので、使用者は深夜割増賃金を支払わなければなりません。(昭和23.10.14 基発第1506号)
関連する解釈例規には、監視断続労働の勤務者について「一定の所定労働時間が定められている場合、その所定労働時間を超えて労働したときに、超過労働に対して幾何の賃金を支払うかは当事者の定めるところによる。」(昭和23.11.25 基収第3052号)としたものがあります。
年休取得と割増賃金
割増賃金の支払が必要かどうかについては、労働基準法が実労働時間主義をとっていることから、1日の労働時間が8時間を超えるかどうかによります。
その原則でいうならば、実際の労働時間が8時間を超えない限り割増賃金を支払う必要はありません。
半日単位の有給休暇(例外扱いとして分割が許される)を取得した人が、有給休暇取得後残業した場合、法的には労働時間が8時間を超えない限り、割増賃金は不要だということになります。
ただし、不要なのは割増賃金であって、通常の労働時間に対して支払われる賃金(100分の100)を支払う義務があることは、いうまでもありません。
